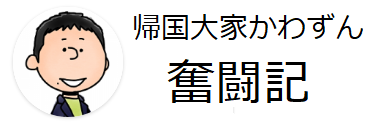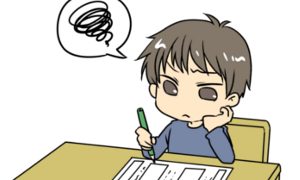面接でクイズのような質問を聞く会社って結構ありますよね。
ちょっと検索してみたところ、以下のサイトでそんな難問・奇問の例が紹介されていました。
就活生必見!面接で良くある難問・奇問30問を集中解説! | 就活の答え
上のサイトで紹介されている難問・奇問のトップ10は以下のようなものです。
- 自分を何かに例えるとすると何ですか?
- あなたを動物に例えるとしたら、どんな動物ですか?
- あなたをSMAPのメンバーに例えると誰が一番近いと思いますか?
- 一日芸能人になれるとしたら、誰になって、何をしたいですか?
- あなたの人生を一言で表してください
- 今日はどうやってここに来ましたか?
- 死ぬときに何を考えると思いますか?
- 面白い話をしてみてください
- 喧嘩をしたことがありますか?
- あなたは今、殴りたいくらい嫌いな人がいますか?
なお、上記のサイトではこれらの質問の意図と回答方法まで掲載されているので興味がある方は見てみてください。
私が新卒で就活をした頃はこんな質問をする会社は無かったと思いますが、こういうのが流行りなのでしょうね。
実を言うと、私は以前からこれらの不可思議な質問に対して「本当にこんな質問で職務に対する応募者の適性や能力が計れるのか?」ととても疑問に思っていました。
難問・奇問では仕事の成果は計れない
もっとも、こういう奇問を問う面接をグーグルがやっているというのは結構有名な話で、「天才の集まるグーグルがやっているのだから私の考えは間違っているのかも」と思っていました。
私の以前の記事「【就活の面接で嘘を付けない?】なぜ日本の就活では嘘をつかなければならないのか?」においても、天才ばかりを集めたいグーグルと、その他の「普通の」会社では質問するべき事柄は違うはずなので、グーグルの真似をして奇問を出したところで意味は無いだろうと指摘しました。
そして今日、なかなか良い記事を見つけたので紹介したいと思います↓
日本の採用面接が人をちゃんと見抜けない理由 | 就職・転職 | 東洋経済オンライン
副題は「あのグーグルも『面接の価値』を否定した」です。
中々興味深くないですか?
記事中で、グーグルの会長が述べたこととして以下のように書いています。
グーグルも以前は難問奇問を出す面接を行っていました。例えば「富士山を動かすにはどうしたらよいと思いますか?」といった奇抜な質問を唐突にぶつけ、それに対する応答で頭の回転のよさを測っていたのです。ところがその面接の得点と入社してからの成果には因果関係がないことがのちに判明し、そのような面接を廃止したそうです。
奇問に対する私の疑問は正しかったということですね。
天才のグーグルより私のほうが分かってるじゃないか!(笑)
・・・と言う冗談はさておき、グーグルは現在ではトライ&エラーを重ねて膨大なデータを収集・分析し、最善の方法を導き出して人事に生かす「ピープルアナリティクス」と呼ばれる手法を導入しているそうです。
詳細は分かりませんが、さすが情報を扱うプロフェッショナルのグーグルといったところですね。
未だに難問・奇問を聞き続ける日本企業
そもそも、難問・奇問を日本企業が面接で聞き始めたのは少なからずグーグルに影響されているのではないかと私は考えています。
そして、当のグーグルはとっくの昔にその間違いに気付き、より理論的で高度な手法を採用し始めているのに、未だにクイズのような質問をしている日本の人事や面接官は職務怠慢としか言いようがありません。
人事の素人の私でさえこれらの質問に対する効果に疑問を持っていたのに、彼らは何の疑問も無く同じような奇抜な質問を面接で繰り返していたのでしょうか?
その面接で採用した人材が本当に成果を上げているのなら別ですが、そうでないのならその面接の仕組みや質問を修正していくべきでしょう。
こういった採用方法の効果(採用した人材が出した成果)の定期的なチェックをしていたら、グーグルのようにその効果に疑問を持ち、奇抜な質問をするような面接はとっくにやめているはずです。
つまり、彼らはそういった非常に重要なチェックをせず、採用方法を改善しようとせず、ひたすら前年度と同じ面接と質問を繰り返しているということになります。
会社に利益をもたらす良い人材を採用するという任務を担っている人事としては、このような状況は職務怠慢と言われても仕方がないでしょう。
面接は面接官が下らない質問をして応募者の面白おかしい回答を集めて楽しむ場ではなく、誰が会社に一番利益をもたらしてくれるかを真剣に判断する場です。
ちなみに、質問する事柄も体系化されておらず、面接官によってバラバラと言うのが現状のようです↓
「面接」は科学的に妥当性が低い
一方、日本企業の多くで行われているフリートーク面接には、そのような評価基準がありません。面接官によって出される質問も下される評価もバラバラでは、公平かつ適切な判断が安定的に行えるはずもなく、つまりはそれだけ精度が低いのです。
古臭い上に非理論的で、いかにも日本企業的なダサさが滲み出ていますね(笑)
グーグルと比べるのは酷ですが、せめてもう少し研究・調査してまともな質問をするようになって欲しいものです。
面接でこんな質問をしている会社のレベルなど知れたものですし、わざわざ時間とお金をかけて面接に来てくれている応募者にも失礼というものです。
面接に落ちても悲観する必要無し
面接で落ちても悲観する必要なんて全然ありません。
冒頭で紹介した東洋経済オンラインの筆者は以下のように言っています。
気合いを入れて面接に臨んだものの、ほどなくしてお祈りメール――「今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます」などと締めることでおなじみの不採用通知が、極めて事務的に届けられる。そんなことが何度も続くと、まるで自分の存在を全否定されたかのような、暗澹たる気持ちを抱く人もいることでしょう。
でも、悲観する必要はまったくありません。なぜなら「面接」という営み自体が、多分に問題をはらんでいるから。多くの日本企業で行われている採用時の面接は、精度も妥当性も低い、穴だらけのシステムだからです。そんなもので、あなたの価値や可能性がまともに測れるわけがありません。
面接に落ち続けたからといって、決してあなたの人格まで否定されたわけではない、ということでもあります。あなたはただ単に、矛盾や理不尽だらけの「面接」という、かなり高難易度なムリゲーに放り込まれてしまっただけなのです。
面接自体が採用の妥当な仕組みではないというのがこの東洋経済オンラインの記事の筆者の主張なわけですが、少なくとも、難問・奇問を出してくるような会社の面接で落とされたのであれば全く落ち込む必要はありません。
なぜなら、そんな面接であなたの実力や、ましてや価値を計ることなどできませんし、さらに言うなら、そんな下らない質問を未だにする職務怠慢な面接官がいるような会社にはそもそも行く価値は無いからです。
「そんな会社に採用されなくてラッキー!」くらいに考えたほうが良いでしょう。
採用・就活というのは会社と応募者のマッチングであり、会社が上から目線で「雇ってやる」「給料を払ってやる」という一方的なものではなく、応募者側も「この会社で働く価値はあるか」という目線で値踏みをし、対等の立場で会社の選別を行うのが就活であることを忘れてはいけません。
そう考えると、こういった奇問を使ってくる会社は候補から外すほうが賢明なのです。
ところで、面接においては志望動機に対して「自己実現のため」とか様々な「ウソ」が飛び交うわけですが、なぜ面接でこんな嘘を付かないとならないのか、そのシステムに疑問に思う人が少なからずいると思います。
その原因は学生のせいでありません。
そんな話に興味があったら以下の記事を読んでください。

>>【就活の面接で嘘を付けない?】なぜ日本の就活では嘘をつかなければならないのか?